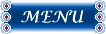| ぽろぽろ |
|---|
|
パーティは疲労のきわみにあった。毎日続く戦闘。息もつけないほどの緊張感の毎日。 ソロは、もう今日は戦闘は休まなくてはと思い、しばらくサランの町に滞在することにした。 昨日はサントハイム城で、バルザックと長い戦いの末勝利をおさめたが、城の人々は戻ってこなかった。落胆したアリーナたちを見ると、ソロにはその気持ちがよくわかって辛いものがあった。 アリーナはサントハイム城に来ていた。勇者一行はサランで武器調達をしたり、宿でゆっくり休んでいた。 しかし、どうしてもアリーナはサントハイム城を見たかった。 今は魔物の巣窟のサントハイム城も、アリーナには懐かしい。 聖水を使ったので、しばらくモンスターはアリーナに近づけなかった。もちろん今のアリーナには、ここのモンスターなどなんでもないが、一人きりの時間を邪魔されたくなかった。 中庭に出てみる。 この庭でアリーナは勉強をサボってはクリフトを困らせたり、兵士相手に武術の練習を始めブライや国王を嘆かせたものだ。花が咲き乱れた中庭は、アリーナのお気に入りの場所だった。 しかし今、ここは花は踏みにじられ、美しい装飾のほどこされた柱はなぎ倒されて見る影もない。 ベンチに腰掛けため息をついた。なんだか悲しくて、みんなと一緒のときは決して見せない涙が止まらなくなった。 ぽろぽろぽろぽろ。 どうしてこんなに涙が止まらないのか、アリーナにもわからない。 ただ次から次へと涙があふれてくる。 ぽろぽろぽろぽろ。 前にアリーナが寝ころがった芝生に涙が吸い込まれていく。それを見ていると余計涙腺が緩む。嗚咽になっていた。 「お父様…。大臣…神父様…城のみんな……。どこ行っちゃったのよ、私を一人置いて…。お父様、私を叱ってよ、今すぐここに来てよ…」 泣きじゃくりながら、周りを見ると、もちろん誰もいなくてモンスターだけが我が者顔に歩いている。 泣きはじめてからどれだけ時間が経っただろう。 アリーナは眠くなってきた。聖水の効き目もやがて切れる。 眠ってはいけない、サランに戻らなくては、そう思うのだが、泣き腫らしてまぶたとまぶたがくっつきそうになっている目と、疲れきった体は言うことを聞いてくれなかった。 アリーナはベンチに横たわった。 それからどれくらい経ったのだろう。気づくとアリーナは自分のベッドで寝ていた。 そしてクリフトが目の前の椅子に座って本を読んでいる。クリフトが顔を上げた。 「お目覚めにになりましたか?」 「あ、あれ?どうして?どうして私、ここに?」 「姫様はベンチでぐっすり眠っておいででした。さしでがましいとは思いましたが、姫様をここにお連れいたしました。あそこでお休みになっていては、いつモンスターに襲われるかわかったものではありません」 まだ頭がはっきりしない。泣きすぎたせいで、頭が重い。 「クリフト、サランで休んでたんじゃ?」 「ちょっと自分の部屋に大切な忘れ物をしたことを、先ほど急に思い出したのです。それで城に参りましたら姫様が眠っておられました」 急に思い出すなんてそんなのは大した忘れ物ではない。 クリフトはあまり嘘がうまくない。忘れ物なんて嘘に決まっている。 だがアリーナはあまり頭がうまく働いていないせいで、それには気づかなかった。 「そうなんだ、私あのベンチで眠ってたのね……え?じゃ、じゃあクリフトがここまで運んでくれたの?」 「失礼いたしました」 「あ、そうじゃなくて」 アリーナはクリフトをじっと見た。 クリフトは男性にしては細い。その体で自分を抱きかかえたまま、3階まで上がってこられたのだ。 クリフトはアリーナにまじまじと見られて、顔に血が上ってくるのを感じる。 「あの、姫様、私の顔に何かついておりますか」 「クリフトって意外と力持ちなのね。びっくりしちゃった」 クリフトは苦笑した。 「一応男をやっておりますので」 「そうね、これは失礼いたしました」 アリーナはクリフトの口真似をして、笑った。 「姫様」 「何?」 「姫様は一人ではございません」 アリーナの顔は一瞬青くなり、そして赤くなった。 さっきの醜態(と自分では思う)を見られたのかと思うと、それを黙って見ていたクリフトに憎悪の念さえ沸く。 「人が泣いているところを盗み見していたのね、ひどいわ、クリフトは」 「姫様、そうではございません」 「だって私は涙を見せないようにしてたのよ、それなのに、それなのに…。泣いてるところを人に見られたくなかった、いるなら声をかけてくれればいいじゃない。覗き見するなんてクリフトって悪趣味だわ!」 「泣きたい時は涙が枯れるまで泣いた方がいいのです。そのほうがすっきりしますから。ですから声をかけなかったのです」 「………」 「姫様はとてもお強い方です。いつもみんなの先頭にたって、戦っておられます。でも戦闘での強さを、自分の心の強さに置き換えることは、なさらないでよろしいのではありませんか」 「…どういうこと」 「自分で自分のことを強い心の持ち主だと決め付けないでください、と申し上げているのです」 「なんか失礼な言い方ね。私がいつもめそめそしてるみたいじゃない」 「言葉が足りなかったのならお詫びいたします。でも、姫様。心が風邪を引くこともあります。泣きたいのをこらえて、苦しい思いをなさらなくていいのです。涙を人に見せてしまってもそれは恥ずかしいことではありません」 「恥ずかしいわ」 「少なくともこのクリフトの前では、弱い部分をお見せになっても恥ではありません。姫様がお辛いのは、私にもよくわかっております」 「………」 「ですが辛い思いをしているのは姫様だけではありません」 「………」 「ソロさんも村の方々をすべて失っておいでです。ライアンさんは、親しいご友人をなくされました。マーニャさんたちは、ようやくお父君の仇を取られましたが、それで悲しみが消えるということはないでしょう」 「………」 「でも皆さんはもっと素直に涙を流されておられます」 アリーナは噴き出した。 クリフトの言い方がおかしかったのだ。笑うところではないと思いつつも、こらえられなかった。 「なに、その言い方」 「姫様、だから泣きたい時は存分に涙を流されてください。そしてその後は笑顔をお見せください。姫様は笑顔のほうが素敵ですよ」 「そんな風に思われてるから泣けないのよね」 「あ、いえいえ、その、私の前では、どんどんお泣きになってください」 またアリーナは噴き出した。 「少しは気分がよくなりましたか?」 「え?」 「たくさん泣いてたくさん眠る。悲しみは消えませんが、それでも心はずっと楽になります。悲しいときはたくさん泣いて心を楽にしてあげるのです。心の風邪はホイミでは治りません。悲しいときには泣けるだけ泣いてください。私がおそばにおりますから」 「…そうする」 「それに、先ほども申しましたが、姫様はお一人ではありません。皆さん心を一つにして悪と戦っているのです」 「うん、そうよね」 「はい」 「クリフトが私のそばにいるのよね、これからもずっとずっと」 「ええ、ずっと姫様のおそばに…って、その、そういう意味では」 「ううん、クリフトがいないと私泣きたいときに泣けないじゃない。ね、ずっとそばにいてね、約束よ」 「はい」 クリフトの頬に赤味が差したのをアリーナは気づかない。しばらくアリーナは天井を見つめていた。そしてクリフトのほうに向き直った。 「姫様」 「いいの、もう大丈夫。泣くだけ泣いたらすっきりしちゃった」 「何よりでございます」 「じゃあ、ちょっと魔物と一戦交えてこようかな!」 「聖水ももうございません。私も賛成です」 「あ、その前に」 「何でしょう」 「クリフトも悲しくて涙が止まらないことがあったの?」 「いえ、もう慣れました」 「?」 「それに悲しくはないのです、今は」 「??」 「でも覚えておいてください。姫様が悲しいときは私も悲しいのです」 「うん、わかった」 クリフトはアリーナの手を取りベッドから起こした。 「お姫様みたいね」 「お姫様です」 「ふふっ、そうだった」 ドアを開けると、モンスターの襲撃。アリーナとクリフトは、うっぷん晴らしのように次々と倒していった。サランに戻る頃には、二人の手にはたくさんのゴールド。 |