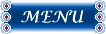| 退屈 |
|---|
|
「毎日退屈だわ」 アリーナはテーブルにうつぶせになり上半身を預けて、ぽつんとつぶやいた。 世界は導かれし者たちの活躍で平和になった。 魔物も出てこない。 どんなに人々が遠出しようとも、強い魔物にやられることもなくなった。 でもそれは、このサントハイム国の王女には、死ぬほど退屈なことでしかなかったのだ。 武術大会が毎年エンドールで開かれるようになった。 先日は2回目の大会開催ということで呼ばれた。 しかし、それにアリーナは参加できない。他の参加者が誰も勝てないからだ。 アリーナは、初優勝者という名誉を与えられて、コロシアムの玉座から試合を見るだけだ。 サントハイムには、以前よりたくさんの近衛兵がおかれるようになった。 万一魔物に攻められても、城を明け渡すことのないようにと。 アリーナがかつて望んでいたように、バトランドほどではないにしろ、兵士が増えたのだ。 しかし3ヶ月もすると、どんな剣の使い手もアリーナに勝てないことがわかり、誰も手合わせをしてくれなくなった。 クリフトは神父になるため、猛勉強中だ。 昔のように、お茶にも誘ってくれない。 ブライは、やっとたまった魔法書を読めるとばかり、図書室にこもりっきりだ。 国王はというと、アリーナを見るたびに、勉強しろという。 おまえはサントハイム国の女王になるのだから。 退屈で死にそう。 冒険にもう一度出たい。 私の世界は、こんな小さな世界じゃないもの。 サランまで散歩に出る。 「あ、王女様だ!」 「アリーナ様、ごきげんいかがですか」 「国王陛下はお元気でいらっしゃいますか」 気さくに話し掛けてくる街の人々と話をしながら、なんとなく裏の看板の方に行ってみた。 看板の前で一人の老人が孫と話をしている。 「この看板は、今の国王陛下がお小さいころ…」 「おじいちゃんが立てたんでしょ、もう何十回聞かされたかわかんないよ」 「すまんの、ついつい……。しかし、平和になってよかったの」 「うん、これも王女様のおかげだよね」 「うむ、アリーナ姫様はよくおやりになった。わしも鼻が高い」 「おじいちゃんには関係ないじゃん」 「何を言う。わしがここにこれを立てたから、今の平和があるのじゃ、お前もわしに感謝すべきじゃ」 「なんで!それ、こじつけすぎだよ。でも王女様がこんな時間を連れてきてくれたんだね」 「そうじゃ。毎日町の外に散歩に行ける。こんな時間さえわしらには持てなかった。普通の生活がどんなに待ち遠しかったか知れなかった。魔物のいない生活こそが普通の生活なのに、それさえ気づかないほど、わしらは不幸せじゃった」 「うん。昨日と変わらない生活が過ごせるってほんとに幸せなんだよね。魔物のいない今、ほんとにそう思う。魔物にビクビクして過ごす生活は、しんどかった。それからするとなんて幸せなんだろう」 「平凡な毎日が過ごせるというのは、最高の贅沢なんじゃよ。アリーナ姫様はそれをわしらに連れてきてくださったのじゃな。さ、今日はテンペあたりまで足を伸ばすかの」 「おじいちゃん、歩けるの、無理じゃん」 「何を言う。このわしはな」 「もういいよ、ほら行こ」 二人が去ったあと、看板の前にアリーナは立った。 平凡な日々が幸せだなんて。 退屈な日々が最高の贅沢だなんて。 知らなかった。 やっぱり私は恵まれすぎているのだ。 そんなことにさえ気づかなかった。 「姫様?」 振り返ると、クリフトが立っていた。 「あれ、どうしたの?」 「お茶でもどうか、と姫様をお迎えに上がりましたら、お部屋においでではなかったので」 「ええー?珍しいわね」 「すみません、少し勉強にかかりっきりで。あと、やっと、この花が」 小さな鉢植えをクリフトは差し出す。 「カミツレ草?きれいに咲いたわね、とてもかわいいわ」 「ええ、今日はこのカモミールティーにしましょう。フレッシュティーで」 「うん。ねえ、クリフト」 「はい?」 「幸せを見つけ出すのは、簡単なことなのに、意外と誰も気づかないことなのね」 「え?」 「今の自分に満足してはいけないけれど、いたずらに不幸ばかり数えてもいけないのだと、そう思ったの」 「どうなさったのです」 「こんなふうに、クリフトが気を使ってくれている、それさえも忘れてたりね」 「ええ?すみません、仰る意味がよく…」 「ふふ、幸せを見つけ出す努力をしていなかったの、私。それがわかったのよ。昨日と同じ日はないのよね、似ている日ではあっても」 「???」 「なんでもないわ、さ、帰ってお茶にしよう!」 「そうですね」 ありがとう。 退屈な日々ではないと気づかせてくれて。 幸せな日々を過ごしていると気づかせてくれて。 サランの人にも。 サントハイムのみんなにも。 お父様にも。 クリフトにも。 幸せな日々の中にいると、その幸せに気づかない。 小さすぎて見失ってしまう。 ごめんね。 そんなことさえ気づかなくて。 私の大好きな人たち。 私の大好きな人。 少し先を歩く緑の神官服が自分の持つ鉢植えのカミツレ草にとても似合って、そんななんでもないことが本当に幸せなんだ。 退屈って最高の幸せなのだな。 そう思ってひとり柔らかく笑うと、立ち止まっていた目の前の青年がやっぱり笑っていて。 アリーナは顔に血が上るのをはっきり感じた。 |