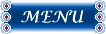|
二人はまたしばらく黙って歩いた。 ふとアリーナが言った。 「ねえ、クリフト。人間って一人では何にもできないのなら、どうして存在する意味があるのかしら」 「哲学的ですね」 「神様に聞いてみたいわ」 「少なくとも姫様は存在する意味がおありですよ」 「どういうこと?」 「ブライ様も私も、姫様のお手伝いをするためにお仕えしているのです」 「まあ、そうだけど」 「つまりは姫様のご存在自体が、何かをなされておられるのですよ、私たちにとって」 「???」 「そして私にとっても――」 「クリフトにとって?」 「いえ、何でもありません」 「言いかけてやめるなんて、すっきりしないわね」 「何でもないんですよ、ほんとに」 クリフトは星空を見上げた。 (あなたがここに存在しているから。あなたの存在こそが、私の生きていく歓びなのです) 「綺麗ね、星が」 「え?」 「星を見てたんでしょ?星が降ってくるみたいね」 「姫様」 「何?」 「私は姫様がいないと何もできない人間ですよ。姫様がいないときっと無力で」 「えっ?何それ???」 「――戻ったら料理の練習なさいますか?」 「はぐらかして。まあいいわ。そうね、練習して今度クリフトにご馳走する」 「ありがとうございます」 火が見えてきた。 「遅くなってしまいましたね。みなさん待ちくたびれておられるでしょうか?」 返事が返ってこなかったのでクリフトはアリーナを見た。 アリーナは少し考え込んでいたが、いきなり口を開いた。 「わかったわ、私にできること」 「何でしたか?」 「うんと強くなることならきっとできるわ!」 クリフトは苦笑した。 「そうですね。それはきっと」 「そして国を守るのよ!」 「え?」 「すっごく強くなってサントハイムを魔物の侵略から守り通すわ。だってそれは大事な人たちを守ることだもの!」 「そうですね、その通りです」 「特にひ弱な誰かは私が守らないとダメだものね!頑張って強くなるわ!それが私の、私にしかできないことよね!」 「ひ弱な誰か…?あの、それは」 アリーナは駆け出した。 「みんなー、薪拾ってきたわよー!」 元気いっぱいのアリーナの声が魔物を呼び寄せてしまい、夕食を前に一乱闘しなくてはならなかったことを付け加えておこう。 |
 小説入り口
小説入り口