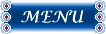|
アリーナはくすっと笑った。その笑顔がクリフトにはたまらなかった。 「姫様」 「何?」 「今からでは遅すぎますか?プロポーズは」 「えっ!あ、してくれるんだー!そうよー、ちゃんと言わなくちゃ」 クリフトはベンチから立ち上がり、アリーナのほうを向くと膝を折った。アリーナの手を取る。 「姫様、このクリフトでよければ、結婚してくださいますか?」 「いいえ」 クリフトは思わず顔を上げた。アリーナは微笑んでいる。 「『クリフトでよければ』ではダメなの。私には『クリフトしかいない』の。言い直し」 「……。姫様。私には姫様しかおりません。姫様にも私しかいないと存じます。ですから私たちは結婚しかありません。結婚いたしましょう」 「…まあまあかな。あんまりいじめちゃいけないもんね」 「そうですよ」 クリフトは真っ赤になっていた。 アリーナも顔に血が上がってくるのを感じた。 二人同時に立ち上がって、歩き始めた。少し風に当たらないといけない。 クリフトはふと思い出して尋ねた。 「姫様。今日はなぜエンドールまで?」 「あのね、お母様のヴェールを仕立て屋さんに持っていったの」 「ヴェール…」 「お母様がお父様と結婚なさった時に、そのヴェールをかぶっていらしたの。すごく綺麗なレースが使ってあるのよ。この間、お父様がはじめて見せてくださったの」 「それではそのヴェールは王妃様の形見なのですね」 「そうなの。お父様は私が結婚するとき、私にくださるておっしゃったの」 「そうですか」 「昨日ね、お父様がヴェールをエンドールの仕立て屋さんに出して来いとおっしゃったの」 「ええ」 「帰ってくる頃には、クリフトに結婚を承諾させておくって」 「…!そ、そうだったんですか」 「ほんとはクリフトに直接言って欲しかったんだよ」 「姫様…」 ふとクリフトに疑問が浮かんだ。 「国王陛下はなぜそんなにお急ぎなのでしょう?」 「半年後の今日ね」 「はい」 「お父様のお誕生日なの」 「?」 「毎年毎年、お父様はお祝いの方々に、自分の見た幸せな予知夢をおっしゃるわ。そしてそれはよく当たるの」 「そうですね」 「それがどうしても今年は私の結婚式しか、夢に出てこないっておっしゃるの。毎晩毎晩ご覧になるの」 「?」 「私がお母様のヴェールをかぶって式を挙げてるの。私の隣には、青い髪にサファイアブルーの瞳の青年が立っている夢なんですって」 「!」 「その夢にお母様が出てこられるの。お母様が『いいかげんアリーナの相手にお気づきなさい』って、お父様に毎晩おっしゃってらしたそうよ」 「……王妃様が」 「あまりに毎晩なので、お父様もお気づきになるわよね、私の…」 「姫様の?」 アリーナは、クリフトに言った。 「あのね、私の名前は『姫様』じゃないの。アリーナなの。アリーナと呼びなさい。これは王女命令です」 「…アリーナ…」 「そう。それから私の王子様!…キスしよう!」 クリフトはついに気を失った。 半年後、サントハイム領の教会中の鐘が鳴り響く。 |
クリフトの髪と瞳の色は、私の中ではずっとファミコンのイラストのままです。
 小説入り口
小説入り口