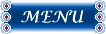|
「クリフト?」 「姫様」 「どうしたの、こんな真夜中」 「なんだか眠れなくて」 「そうなんだ、私もなんだ」 「姫様、その鏡は?」 「あ。えっと、ミネアに借りたの」 「姫様もですか?」 「クリフトも?なんで?」 「なんでって、それはその」 「私はね、ある人の想いを確かめたかったの」 「そうですか」 「でも何も映らなかったのよ、クリフトも、そういうことで借りたんでしょ?ねえ、映った?」 「いえ」 「な〜んだ、そうなんだ、お互い様だね」 「どういう方なのです?姫様の想い人は」 「やあねえ、それ、難しい言葉ではプライバシーの侵害とかいうんですってよ。だったら、クリフトが先に言いなさいよ」 誰がそういう言葉を教えたのか、とクリフトは苦笑したが、だいたい見当はついたので聞き返さなかった。その代わり、別の質問をする。 「その前に。姫様、昨夜どうして私が女性と会ったとお思いになったんですか」 「え?うん。香水の香りがしたの」 「は?(ああ、そういえば、香が焚きこめてあった…)」 「だからクリフトは誰かにあってきたんだなあ、と思って。すごく辛くて。ついこの鏡を見てしまったってわけ。―――あ!」 「姫様?」 「あ、あ、あの、そのね。違うの!クリフト、気を悪くしないでね」 「気を悪くするわけないじゃないですか」 「え?えと」 「いい鏡ですね、それ」 「あ…」 バルコニーで下を眺めプライバシーの侵害をしている、ミネアとマーニャ。 マーニャが尋ねた。 「ねえ、あの鏡なんなのよ」 「魔法の鏡よ」 「うそつけ」 「うふふ、あのね、両思いのカップルが、あの鏡を覗き込むと好きな人に会いたくなるの」 「ええ、ほんと?」 「好きな人に気持ちを話さずにはいられない、香が焚きこめてあるの」 「へー、そんなすごい香なら、鏡つきでじゃんじゃん売り出せばいいのに。きっとすっごく儲かるよ!でさあ、カジノにガンガンつぎ込んで、その儲けでまた鏡売り出して!あんたの占いよりずっと儲かるわよ!」 「……姉さんって人は」 「そんなマジになんなくったって」 「まあ、お二人が上手くいきそうでよかったですわね」 「何がよかったよ、あーあ、人の恋愛成就見たってつまんないわねー、まったく金持ちのいい男ってどこにいるんだか。早く父さんの仇討って、あたしもラクチンな人生送らなくちゃ。さ、寝よ寝よ」 マーニャの去ったバルコニーで、ミネアは、少しは遊び癖の治る香を調合せねばと決意するのだった。 |