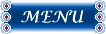| 刺繍 |
|---|
|
「はー」 「はー」 何度も繰り返されるため息だがだんだん大きくなる。 「姫様。もっと集中してなさらないとケガをしますよ!」 女官長がアリーナを叱る。 「だってこんなのつまんないものー。あーあ外で、体動かしたいなあー」 アリーナはこの部屋でさっきから、刺繍をやっている。いや、やらされている。 貴族の娘は、刺繍を趣味にするものも多い。またたしなみとして、身に付けることが半ば習慣である。 もちろんアリーナにとってはこんなつまらないものはない。 ただだらだらと針を動かしているだけである。 そんな調子だから、針を指に刺すのも当然といえば当然である。 「いたぁっ!!」 「ほら!姫様、申し上げたでしょう!!すぐ薬箱をお持ちしますから!」 「ああ、いいわ。クリフトのところに行ってくる。クリフト、ホイミ使えるし」 「姫様!!」 無論抜け出す口実なので、女官長は大声を上げたが、もうアリーナはいない。 いつもは乱暴気味に開ける扉を今日は静かに開けた。だんだん痛くなってきたのだ。血が固まりになってたまってきた。 クリフトは本を読んでいたが、神父が入ってきたのかと思い椅子から立ち上がった。 アリーナを見て驚く。 「姫様?きょうはずいぶんお静…あ、ケガをなさったのですか!」 慌ててアリーナに近寄る。 「うん。ちょっとね、針を刺しちゃって」 「消毒しないといけませんね」 「いいよー、ホイミで。ね、クリフト、ホイミかけて」 「ホイミでは傷口の消毒はできませんので…針を刺したのでしたら、消毒も」 そう言いながらてきぱきと、クリフトは塗り薬などを用意する。 「キアリーじゃだめなのかな?」 「キアリーはモンスターの発する毒を解毒するものですので、これには効かないですね」 「姫様、こちらにお座りください。これはハーブを調合してあって、消毒効果も高いんですよ。指を…」 クリフトはアリーナの指を取って、消毒しながら、黙り込んでしまった。 今までこんな風に、じっくりとアリーナの手をとったことはない。 (姫様の指はこんなにも細かったのだろうか?あの会心の一撃は、こんなか細い指から繰り出されるのだろうか?) 頭に血が上ってくるのがわかる。 アリーナのほうも手をとられて、顔が赤くなり始める。アリーナとしても、こんな風にしっかり手をとられたことがない。 (な、なんで?クリフトに手をとられただけで顔が!?) クリフトに気づかれなければいいのだけど、と思う。 二人とも心臓の鼓動が速くなって、お互いに相手に聞こえてなければいいのだがと思っている。 「消毒はこれでいいですね、ではホイミをかけておきましょう」 アリーナの指にホイミをかけた。 ほっとして、改めてお互いを見ると、治療のせいで、顔と顔がくっつきそうな位置に座っていた。 「あ……」 声にならない声が二人とも出た。急いで少し離れる。 「そもそも、どうして指に針を?」 やっとクリフトは気持ちが落ち着いてきて、質問した。 「うん、刺繍してたのよ。でも私、あんな細かい作業向いてなくって。やっぱり体動かしてたほうがいいわ」 「姫様らしいですね。ただ私は姫様の作品を拝見してみたいとも思いますが」 「そう?」 「はい」 「そういえばここにも刺繍が飾られてるわね」 壁に絹取りの刺繍が飾られている。 「あれは?」 「ああ、昔母が作ったものです」 「お母様が?」 「はい」 「そっか……」 クリフトの両親はすでに亡くなっていた。 クリフトが幼い頃から神官としての道を歩んだのは、自然の流れでもあった。サントハイム城にアリーナの遊び友達として引き取られたその頃から、サラン教会の神父に神の道を学んでいた。 母を亡くしているアリーナには、クリフトの気持ちがよくわかる。 アリーナはいきなり立ち上がった。 「姫様?」 「クリフト、私ちょっと用事があるの!またね!」 それから数日は、アリーナは外にも出ず、ずっと室内にこもりっきりだった。 口さがない商人などは「お姫様はご病気ですか」などという始末。 サントハイム王もブライも、アリーナに何かあったのではと心配するが、食欲はいつものように旺盛だし、元気はありあまっている様子なので「ついに姫も女らしくなって、武術の稽古もやらなくなった」と喜んでいた。 |