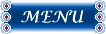| 遠い記憶 |
|---|
|
もうここに住んでどのくらい経つだろう。 その神官は、ふと本から顔を上げると窓に広がる景色を眺めながら、そうつぶやいた。窓一面にスカイブルー一色が迫る。ただただどこまでも青い海と空。ここは、都会の喧騒から置き去りにされた小さな島だ。 神官はここより遠く離れた城付きの教会出身だった。この村の住民からは、とても慕われている。ただ彼は村人に一度も自分の過去を話したことはなかったので、その神官が以前、世界を救った勇者一行の一人だったということは誰も知らなかった。 こうして海を見ていると、彼の中に過ぎ去った遠い日がよみがえる。彼のいた城の近くにも海があった。 その城の王女と、城を抜け出し時々海に出かけた。 その王女を愛していた彼には、今でも彼女の声が聞こえてくる。 いっしょに旅をした日々。こちらの心配はよそに、無謀なことばかりするお姫様。 その頃のことを思い出すと、なぜか彼は微笑んでしまう。 そして、その王女と最後に話した日のことも同時によみがえってくるのだ。 その日もとてもよく晴れた日だった。海面がキラキラしていた。 「結婚式には出席してくれるんでしょう?」 「いえ。私はここを離れようと思っています。どこか小さな村で村人のために尽くしたいと思っています」 「え、そうなの?神父様の手伝いでずっとここにいるのだとばっかり」 「姫様、もうこうして私と会ってはいけません」 「どうして?」 「姫様はもうすぐ結婚なさる方だからです」 「なんで?そんなの関係ないじゃない。ずっと一緒に兄妹のように暮らしてきたんだもの。今までと一緒よ、結婚するから会っちゃいけないなんておかしいわ」 「周りの方が変にお思いになります」 「変なのはそっちのほうよ」 「とにかく私は、1週間後ここを離れますから、もう姫様とお会いすることもないでしょう。姫様、どうぞお幸せに」 「い、1週間後!?ちょ、ちょっとどういうことなの?何でまたそんな急に!」 「国王陛下にも皆様にも、もう申し上げております」 「……!」 「姫様の花嫁姿が見られないのは残念でございますが、もう決めたことですので」 「そんな……私だけ知らなかったのね」 「姫様にお知らせすれば、お引き止めになるかも知れない、と思いましたので」 「……そう。じゃあ勝手にどこへでも行けば」 「姫様、この私は今日まで姫様のおそばでお仕えできたことを、とても幸せに思っております。ありがとうございました。姫様、どうぞ、どうぞお幸せに」 「…………」 「では、私は先に城に戻っておりますので」 「…………」 彼は王女を振り返らなかった。不覚にも涙が出てきそうだった。その彼の後ろ姿に重なる声。 「クリフトのバカーッ!クリフトなんか大嫌い!」 それが愛する王女の声を聞いた最後だった。 いつも思い出してしまう。あれから王女は、幸せに暮らしていると聞いた。 彼、神官クリフトが勤めていたサントハイム城も、きっと今も変わらず、その王女…アリーナの笑い声がこだましているだろう。 なぜか涙がにじんでくる。 「つまらない感傷だ。まだまだ私は未熟だ」 そう言ってクリフトは本をテーブルに置いた。 |